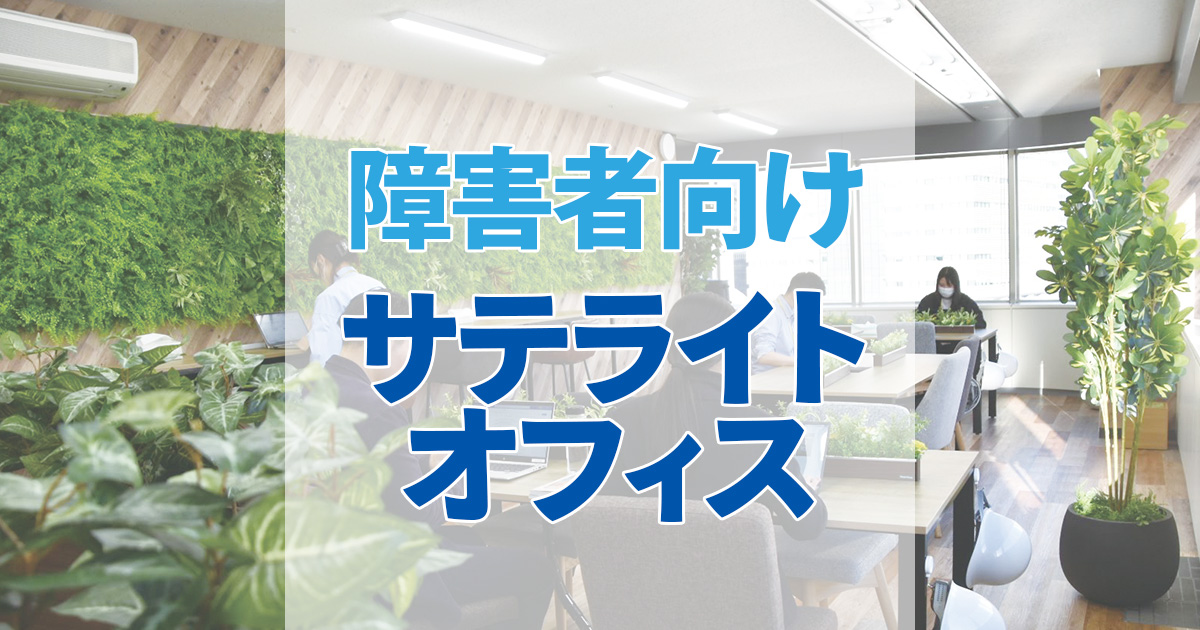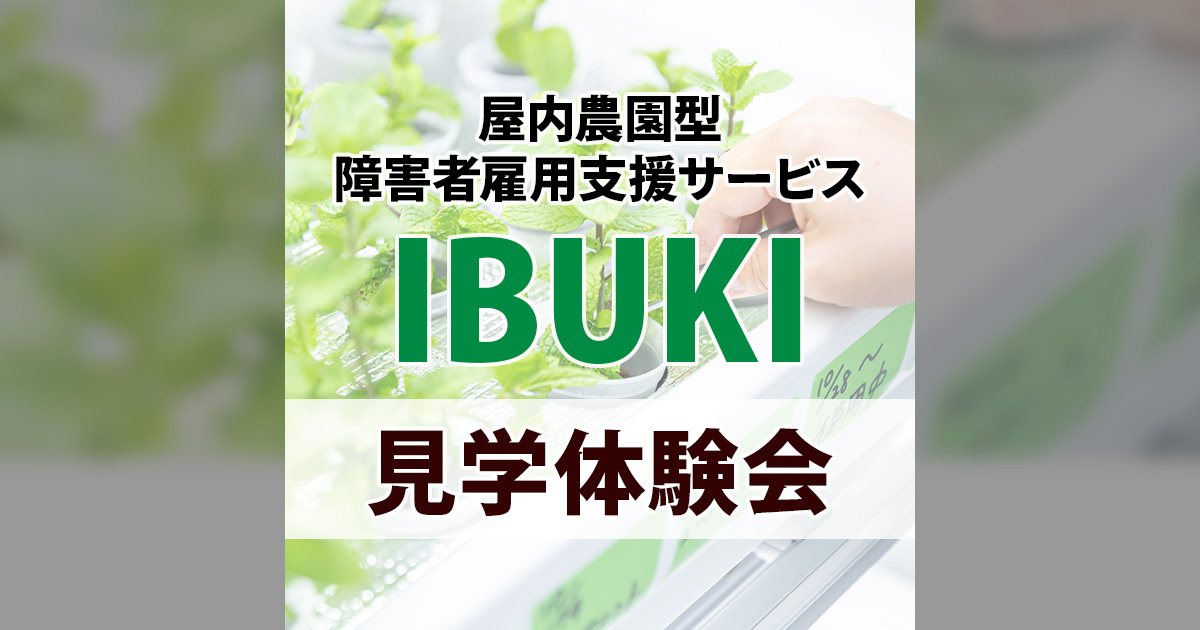障害年金ってどんな制度?
障害年金(注1)は、病気や障害によって働くことや日常生活に支障がある方の生活を支えるための公的制度です。
この制度は、国民年金や厚生年金に加入していた人が、一定の障害状態になった場合に、生活の安定を図るために支給されます。働けない期間の経済的な不安を軽減し、自分らしく生きるための支えになります。
たとえば、うつ病や発達障害などで長期間働けない状態が続いた場合でも、障害年金を受給することで、生活費や医療費の一部をまかなうことができます。無理に働かずに治療に専念できるため、働き方や生き方を見直す余裕が生まれます。
障害年金は、働くことが難しい状況でも「安心して暮らす」ための大切な制度です。
まずは制度の概要を知ることから始めましょう。
※注1参照:日本年金機構「障害年金」

障害年金の対象者と受給条件
障害年金は、一定の条件を満たした方が受給できる制度です。
主な条件は
・初診日が年金加入期間中であること
・保険料納付要件を満たしていること
・障害認定日(注2)に定められた障害等級に該当すること
の3つです。
たとえば、会社員として厚生年金に加入していた方がうつ病で初めて通院した場合、その初診日が加入期間中であれば、障害(厚生)年金の対象になります。
診断書や生活状況の記録が重要な判断材料になります。
※注2参照:日本年金機構「障害認定日」
月々いくら受給できるの?何歳まで?
障害年金の受給額は、年金の種類や障害の等級によって異なります。
障害基礎年金(国民年金加入者)は1級・2級、障害厚生年金(厚生年金加入者)は1級〜3級に分かれており、それぞれ支給額が異なります。
また、扶養家族の有無など、個々のご状況に応じて加算が適用される場合があります。

一般的な等級の区分や、加入状況に応じた受給額を認識しておきましょう。
※注3参照:NPO法人障害年金支援ネットワーク
※注4参照:日本年金機構「老齢年金」
精神障害(うつ病・発達障害など)も受給できる?
精神障害も障害年金の対象です。
うつ病、統合失調症、発達障害なども、日常生活や就労に支障がある場合は障害年金の対象になります。診断書の内容や生活状況の詳細が審査のポイントです。
※ただし、一部の傷病では障害年金の対象外となる可能性があります。
たとえば、精神障害で人間関係や業務遂行に困難があり、就労が継続できない場合、障害年金への該当が考えられるので、受給できる可能性があります。
障害年金に関する制度や受給要件を確認したい場合は、日本年金機構が運営する公的年金に関する窓口機関の「年金事務所」と「街角の年金相談センター」に相談するのもお勧めです。
全国に約400か所あるので、お住まいの地域にあるか調べてみましょう。
働きながら障害年金を受給するためのポイント
障害年金をもらいながら働くことは法律上問題ない?
障害年金を受給しながら働くことは、法律上問題ありません。
実際に多くの方が、障害年金を受給しながら障害者雇用などで働いています。
ただし、働き方によっては障害の程度が軽くなったと判断され、等級が変更される可能性があります。
無理のない範囲で働きながら、定期的に医師の診断を受けることが大切です。
収入制限はある?いくらまで働ける?
障害年金には一部を除き明確な収入制限はありませんが、収入が増えることで「障害の程度が軽くなった」と判断される可能性があります。
特に、障害等級の見直しが行われる際に、就労状況や収入が参考にされる場合があります。
国民年金との関係や支払い義務について
障害年金を受給していても、国民年金の保険料の支払い義務は原則としてあります。
ただし、障害等級が1級または2級に該当する場合は「法定免除」となります。
免除申請は各自治体の窓口で行えますので相談してみましょう。
障害年金受給者の働き方とその選択肢
主な働き方
一般雇用
障害をオープンにせず、一般就労で働く方法です。職種や勤務時間、給与などの選択肢は広いですが、障害への配慮は期待しにくい場合があります。
障害者雇用
障害者雇用制度を活用することで、安心して働ける環境が整います。
企業には合理的配慮の義務があり、業務内容の調整や勤務時間の柔軟化などが可能です。
たとえば、周囲の音が気になり業務に支障がでてしまう方には、耳栓やイヤホンの使用が許可されたり、定期的な通院が必要な場合には、勤務時間の短縮が可能になったりと、特性に合った配慮を受けることで、長く安定して働くことが可能になります。
障害者雇用では、安心して長く働ける可能性が広がります。
その他の働き方
就労福祉支援サービスを利用する働き方
就労継続支援という障害福祉サービスを利用して働く方法です。一般企業での就労が難しい方が対象で、「A型」と「B型」があります。

• 就労継続支援A型
― 事業者と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金が支払われます。
― 週5日、1日4〜6時間など、規則的な働き方が可能です。
• 就労継続支援B型
― 雇用契約を結ばず、勤務時間の自由度があり、体調やペースに合わせて柔軟な働き方が可能です。
― 賃金ではなく「工賃」が支払われるため、A型よりも収入は低い傾向にあります。
詳細として、厚生労働省(注5)のサイトでは、毎年、全国の就労継続支援事業所における平均賃金や工賃の実績が公表されています。参考に確認してみましょう。
※注5参照:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について
在宅で働く方法
通勤が困難な方や、体調に不安がある方のために、在宅での働き方も増えています。

• 在宅勤務(テレワーク):
一般就労や障害者雇用の枠で、在宅での勤務が認められているケース。
• 在宅フリーランス:
個人事業主として、クラウドソーシングなどを活用して働く方法。
• 在宅型就労継続支援:
就労継続支援A型やB型の中には、在宅で作業できる事業所もあります。
これらの選択肢は、障害の程度や体調、本人の希望に応じて選ぶことができ、働きながら障害年金を受給することも可能な場合があります。
安心して働きやすい職場環境のポイント
安心して長く働き続けるためには、ご自身の体調や状況に配慮した環境が不可欠です。
以下のようなポイントが整っているかを確認しましょう。
- 業務内容が明確である
「何をする仕事か」だけでなく、「どこまでが自分の仕事の範囲か」がはっきりしていると、不安なく仕事に取り組めます。また、作業マニュアルが用意されていたり、業務の進め方が可視化されていたりすると、新しいことを覚える際も安心です。 - 相談できる支援者や上司がいる
困ったときに一人で抱え込まず、すぐに相談できる相手がいることは非常に重要です。
精神保健福祉士やジョブコーチなど、専門の支援員が常駐している事業所や、障害への理解がある上司や同僚がいる職場は、安心感につながります。 - 体調に応じて勤務時間や業務量を調整できる
体調の波がある方にとって、無理なく働ける環境は欠かせません。
勤務時間の短縮や、休憩時間をこまめに取ること、あるいは業務量の調整など、柔軟な対応が可能かどうかは、長く働き続ける上で重要なポイントです。
ご自身の体調や状況に配慮した環境が整っていることで、安心して長く働くことができます。
働き先を選定する際には、これらの点が満たされているかを確認してみると良いでしょう。
よくある質問(FAQ)— 障害年金をもらいながら働きたいあなたへ
Q.障害年金を受給していることを職場に伝える必要はある?
障害年金の受給は個人の権利であり、傷病手当金を受給する場合などには年金を受給している事実を会社側が知ることがありますが、会社側に伝える義務はありません。
一方、合理的配慮を受けたい場合や、勤務時間に制限がある場合は、伝えることで職場の理解を得やすくなります。
信頼できる上司や人事担当者に相談することで、働きやすい環境づくりにつながります。
Q.障害年金を受給しながらアルバイトや短時間勤務はできる?
可能です。
障害年金は、働いているかどうかではなく、障害の程度によって支給される制度です。
短時間勤務やアルバイトであれば、障害の状態に大きな変化がなければ受給は継続されることが大半です。
Q.障害年金の更新って何?働いていると不利になる?
障害年金の更新とは、定期的に障害の状態を確認し、支給の継続可否を判断する手続きです。働いていること自体が不利になるわけではありませんが、働き方によっては「障害の程度が軽くなった」と判断される可能性があります。
無理のない働き方を選び、医師の診断書に正確な状況を記載してもらうことが重要です。
Q.障害年金をもらえないケースってどんなとき?
主な理由は、
・初診日が年金加入期間外である
・保険料納付要件を満たしていない
・障害等級に該当しない
などです。
また、診断書の内容が不十分の場合や、生活状況の記録が不足している場合も不支給になることがあります。申請前に条件を確認し、必要書類をしっかり準備しましょう。
Q.障害年金と生活保護は併用できる?どちらを優先すべき?
併用は可能ですが、障害年金は「収入」として扱われるため、生活保護の支給額が減額されることがあります。
基本的には障害年金を優先し、不足分を生活保護で補う形になります。
居住地の福祉課で相談すると、最適な支援の組み合わせを提案してもらえます。
Q.障害年金を受給していると医療費の助成は受けられる?
受けられます。
自立支援医療制度や重度心身障害者医療費助成制度など、障害年金受給者が対象となる医療費助成制度があります。自治体によって内容が異なるため、居住地の福祉課で確認することが大切です。
Q.障害年金の受給中に病状が悪化したらどうすればいい?
病状が悪化した場合は、条件付きではありますが、等級変更の申請が可能です。
医師の診断書を再提出し、障害状態の変化を年金機構に報告することで、支給額が増える可能性もあります。早めに医師に相談してみましょう。
Q.障害年金の申請に必要な診断書ってどんな内容?
診断書には、病名、初診日、障害の状態、日常生活への影響などが詳細に記載されます。
特に「日常生活能力の判定」や「就労状況」の欄は審査に大きく影響する場合が多いです。
医師に申請目的を伝え、正確な内容を記載してもらうことが重要です。
Q.障害年金を受給していると住宅支援や手当は受けられる?
受けられる可能性があります。
公営住宅の優先入居や家賃補助、グループホームの利用など、障害年金受給者向けの住宅支援制度があります。自治体によって制度が異なるため、福祉課で相談してみましょう。
Q.障害年金を受給していると確定申告は必要?
障害年金自体は非課税なので、原則として確定申告は不要です。
ただし、障害年金以外に収入がある場合や、医療費控除などを受けたい場合は申告が必要です。
まとめ:障害年金と働くことは両立できる。自分らしい働き方を見つけよう
障害年金は、働けない期間の生活を支えるだけでなく、「安心して暮らす」ための土台にもなります。
制度を正しく理解し、無理のない範囲で働くことで、経済的にも精神的にも安定した生活を築くことができます。
働き方にはさまざまな選択肢があり、障害者雇用や福祉サービスを活用することで、安心した環境で業務を行うことができます。
また、障害年金を受給しながら働くことは法律上も認められており、収入制限や就労状況に注意すれば、長く両立することが可能です。
「働きたいけど不安がある」「障害年金制度が複雑でよくわからない」と感じている方も、一人ひとりの状況に合った支援や制度が、きっと見つかります。
自分らしく働くために、まずはご自身の状況を整理してみましょう。
働くことに不安がある障害者へ:スタートラインのサービスを紹介
FITIMEで「働く力」を身につけて企業就労を目指そう
360社以上、2300名以上の障害者雇用支援実績のある株式会社スタートラインが運営元の「FITIME(フィティミー)」は、サービス業に特化した就労移行支援サービスです。
飲食・アパレル・販売・清掃など、実際の業務に近い模擬体験を通じて、自分に合った職種を見つける「カラフルトレーニングプログラム」と、実際の仕事を通じて責任感や働く喜びを育む「リアルジョブトレーニングプログラム」の二段階で構成されています。
自分の強みや興味を活かしながら、企業就労に必要なスキルと自信を育てることができます。
安心して長く企業就労で働きたい障害者へ:スタートラインのサービスを紹介
障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス INCLU
「INCLU(インクル)」は、障害者が安心して働ける環境を整えたサポート付きサテライトオフィスです。バリアフリーやセキュリティなどに配慮したオフィス設計に加え、スタートラインのサポートスタッフが常駐しているため、安心して働くことが可能です。
ロースタリー型障害者雇用支援サービス BYSN
「BYSN(バイセン)」は、コーヒーの焙煎や接客を通じて、障害者が働く力を育むロースタリー型の支援サービスです。オリジナルブレンドの開発や販売を通じて、コミュニケーション力や責任感を養いながら、実践的なスキルを身につけることができます。
また、スタートラインのサポートスタッフが常駐しているため、安心して働くことが可能です。
屋内農園型障害者雇用支援サービス IBUKI
「IBUKI(イブキ)」は、屋内農園でハーブ類などを生産・加工する障害者雇用支援サービスです。
ハーブ類などに触れながら、業務を通じてご自身の可能性や、チームワークを育むことができる環境が整っています。スタートラインのサポートスタッフが常駐し、個々の特性に合わせた支援を行うので、安心して働き続けることが可能です。
見学体験会/オンラインオン説明会も都度開催中
INCLU、BYSN、IBUKIでは、見学体験会/オンライン説明会も無料で都度開催しています。
・仕事内容を詳しく知りたい
・どんな人が働いているか気になる
・通勤圏内に拠点があるのか教えて欲しい
など知れる貴重な機会です。
未経験でも安心して働けますので、ご興味ある方は、まずは、以下からご参加ください。