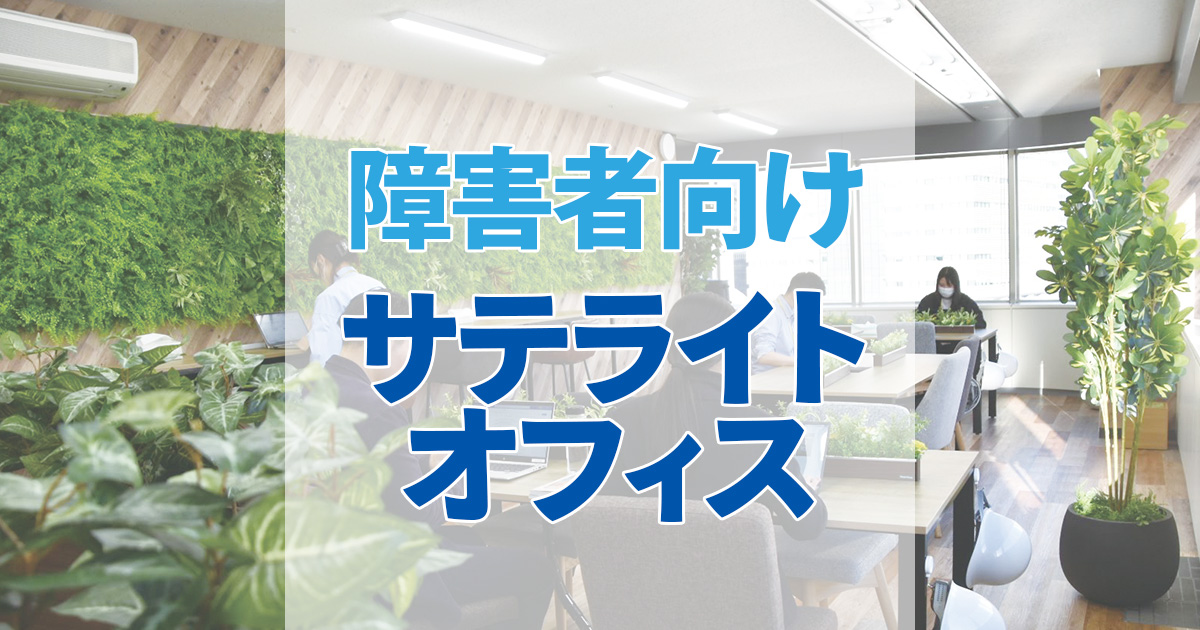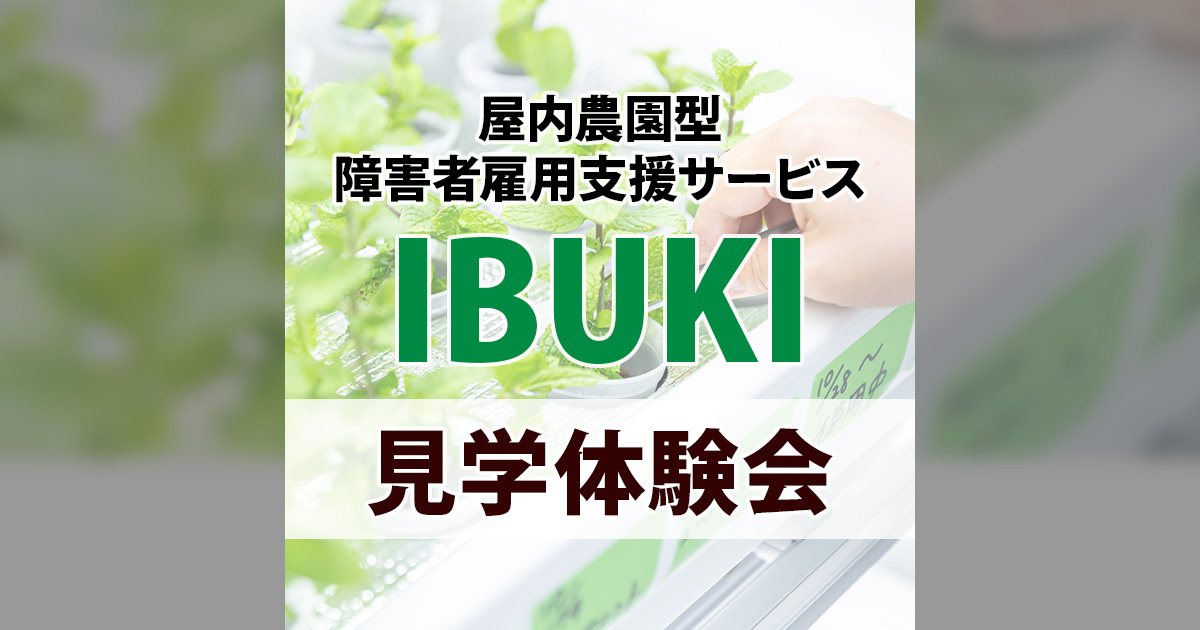障害者雇用の給料の実態とは?
障害者雇用の平均年収と月収
厚生労働省の「障害者雇用状況報告」(注1)によると、障害者雇用の平均年収は約200〜300万円程度で、月収にすると15〜25万円前後が一般的です。
これは、雇用形態が契約社員やパートタイムであることが多く、業務内容も限定的な場合があるためです。
平均年収は、身体障害者は約280万円、知的障害者は約160万、精神障害者は約180万円、発達障害は約160万とされています。
障害者雇用でも安定した収入は得られますが、生活設計には障害年金や支援制度の併用も視野に入れることが重要です。
(注1)参照:令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します|厚生労働省
障害者雇用の給料が一般雇用と比べて低い理由
障害者雇用は、一般雇用と比べて給料が低めに設定される傾向があります。
これは、企業が配慮の一環として業務量を軽減していることや、雇用形態が、契約社員やアルバイトなどの非正規雇用が多いことが背景にあります。
たとえば、障害者雇用での事務補助職では、月収が12〜18万円程度にとどまるケースもあります。
給料の低さは制度や仕組み的な社会課題でもあるため、企業選びや支援制度の活用が重要です。
障害種別による職種・給料の収入傾向
障害種別や程度によって、就ける職種や働き方が異なるため、給料にも差があります。
身体障害者は比較的安定した職種に就きやすく、平均月収も高めな傾向がありますが、知的障害者や精神障害者、発達障害者は、支援付き雇用や短時間勤務が多く、収入は低めになる傾向があります。
ただし、職種によっては専門性を活かして高収入を得ている事例もあり、支援制度や職場環境によって安定した収入を得ることも可能です。
▼障害種別ごとの職種・収入傾向

参照:令和5年度障害者雇用実態調査の結果を公表します|厚生労働省
就労継続支援A型・B型と障害者雇用の給料(賃金/工賃)比較
障害者の働き先によって、給料水準は大きく異なります。
特に、就労継続支援A型・B型と一般企業の障害者雇用で働く場合は、月収に差があるのが現状です。
これは、雇用契約の有無や業務内容、最低賃金の適用範囲が異なるためです。
就労継続支援A型は雇用契約があり最低賃金が保証されますが、B型は工賃という形で支払われ、月収は低い傾向になります。
厚生労働省のデータ(令和5年度)によると、
・就労継続支援A型:平均賃金は月額約 86,752円
・就労継続支援B型:平均工賃は月額約 23,053円
・一般企業の障害者雇用:平均給料は月額約 185,000円
とされています。
このように、どの働き方を選ぶかで収入は大きく変わるため、ご自身の体調や生活環境の希望に合わせた選択が重要です。
就労継続支援A型・B型と就労移行支援の給料(賃金/工賃)の違い
就労継続支援A型・B型を調べると、類似キーワードで就労移行支援を目にすることがあるのではないでしょうか。
就労継続支援A型・B型と、就労移行支援は目的や対象など、全く異なるため、給料(賃金/工賃)に大きな違いがあります。
就労移行支援は「一般就労への準備」が目的であり、訓練や就職のためのサポートを受ける場なので、原則として給料(賃金/工賃)は発生しません。
一方、就労継続支援は「働く場」を提供するため、A型・B型ともに報酬があります。
• 就労移行支援:給料なし(例外的に少額の工賃を支払う事業所あり)
• 就労継続支援A型:雇用契約あり、最低賃金保証、平均月収 約86,752円
• 就労継続支援B型:雇用契約なし、平均工賃 約23,053円
「一般就労を目指したい」けど、その前にしっかり訓練や就職のためのサポートを受けたい場合は、就労移行支援がお勧めです。
障害者雇用で生活できる?支援制度や活用方法を解説
前提として、
・一人暮らし?
・配偶者は?
・賃貸?持ち家?
など、ご自身がどのような生活環境にいるかによって生活できるかの基準が異なるため、一概には言えません。

まずは、ご自身の生活環境をしっかり整理しましょう。
そのうえで、障害年金や自治体の支援制度、副業を組み合わせることで、生活を安定させることは可能なため、しっかりと制度を理解することが大切です。
障害年金の制度と併用
障害年金(注2)は、障害によって生活や就労に制限がある人を支援する制度で、就労と併用することができます。
• 障害基礎年金(1級・2級)(注3):原則として「就労が困難なほどの障害」が要件です。したがって、フルタイム勤務など実態として十分に働けている場合、支給の見直しや停止の対象となる可能性があります。
• 障害厚生年金(1級~3級):1級・2級は上記と同様に、就労が困難な状態が前提です。3級は一定の労働能力があることを前提としていますが、仕事内容や勤務状況によっては見直しの対象となる場合があります。
受給を希望する際は、「収入額」ではなく「障害の程度と就労実態」に矛盾がないことがポイントです。
また、障害年金と併用できる制度として、医療費助成・住民税減免・交通費割引などがあります。
• 医療費助成(マル障):障害者手帳を持つ方は、通院や入院の自己負担が軽減され、住民税非課税世帯なら無料になる自治体もあります。
• 住民税減免(障害者控除):一定の条件において、住民税が最大数十万円控除される制度があり、年末調整や確定申告で申請可能です。
• 交通費割引:障害の区分によって、JRや私鉄、バスの運賃が半額になるほか、航空会社の障害者割引や自治体のタクシー券交付がされることもあります。
これらを組み合わせることで、生活の負担を大きく減らすことができます。
(注2)参照:障害年金|日本年金機構
(注3)参照:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
自治体の支援制度・助成金を活用
国の制度に加えて、自治体独自の給付金や助成制度を活用することも重要です。代表的なものは以下の通りです。
• 特別障害者手当:重度障害者に月額29,590円(2025年度)(注4)
• 障害児福祉手当:20歳未満の重度障害児に月額16,100円(2025年度)(注5)
• 医療費助成制度:自治体ごとに異なる。全国的に「重度心身障がい者医療費助成制度」や「福祉医療費給付事業」などの名称で実施
• 税金の控除:障害者控除:障害者270,000円、特別障害者400,000円、同居特別障害者750,000円(注6)
• 交通費・NHK受信料の割引
さらに、自治体独自の手当や通院交通費助成などもある可能性があるので、住んでいる地域の福祉課で確認することが大切です。
(注4)参照:特別障害者手当について|厚生労働省
(注5)参照:障害児福祉手当について|厚生労働省
(注6)参照:No.1160 障害者控除|国税庁
副業による収入増の可能性
障害者雇用の給与だけでは生活が難しい場合には、副業を組み合わせて収入を補う人もいます。
• おすすめの副業例:Webライティング、データ入力、イラスト制作、動画編集など
• 注意点:
― 勤務先の就業規則で副業が許可されているか確認
― 体調管理を最優先にする
― 副業収入が年間200,000円を超える場合は確定申告が必要
― 障害年金受給中の場合、働き方によっては支給停止のリスクがあるため、医師や専門家に相談することが望ましい
副業は、無理なく続けられる範囲で始めることが成功のカギです。
特に注意点の「体調管理を最優先にする」はとても大切ですので、ご自身の体調と相談しながら、ご自身のペースで検討してみましょう。
障害者雇用の昇給・キャリアアップの可能性
障害者雇用でも、昇給やキャリアアップは十分に可能です。
昇給制度がある企業の特徴
障害者雇用で昇給を期待するなら、以下の特徴を持つ企業を選ぶことがポイントです。
• 人事考課制度が整っている企業:目標管理や評価基準が明確で、成果に応じて昇給が決まる
• 定期昇給制度がある企業:年功序列型や勤続年数に応じた昇給制度を導入している
• 合理的配慮とキャリア支援を両立している企業:特例子会社や大手企業に多く、昇給・昇進の事例も豊富
• 昇給・賞与の実績を公開している企業:求人票や面接で確認可能
実際、聴覚障害を持つ社員が、手話通訳やICTツールのサポートを受けながら、入社3年で昇進した事例もあります。
スキルアップで年収を上げる方法
障害者雇用で年収を上げるためには、スキルアップが欠かせません。
具体的な方法は以下の通りです。
• 資格取得:MOS、簿記、ITパスポートなど、事務・IT系資格は評価対象としてわかりやすい
• 専門スキルの習得:プログラミング、デザイン、データ分析など、専門性の高いスキルは就活市場で有利
• 正社員登用を目指す:契約社員やパートから正社員になると、昇給・賞与支給などが見込める(※福利厚生は原則パートアルバイトも同じ)
特に、正社員を目指すことで、年収が大幅にアップするケースもありますが、無理は体調に良くないので、まずは安定して働くことを優先しましょう。
障害者雇用から一般雇用への転換事例
障害者雇用から一般雇用に切り替えることで、キャリアの幅を広げる人も増えています。
・事例1:精神障害者が障害者雇用枠で入社後、業務実績と医師の意見書をもとに、一般雇用へ転換。給与も段階的にアップし、正社員として活躍。
・事例2:物流業界で障害者雇用からスタートし、スキルを積んでIT企業に転職。
心身の状態も安定し、現在は大手企業で一般雇用の正社員として勤務。
このように、スキルと実績を積み重ねながら、自分自身で働きやすい環境を模索し、心身の状態を整えたうえで、障害者雇用から一般雇用へのキャリアチェンジは十分に可能です。
一般雇用に転換を検討する場合は、ご自身の体調に合わせて、無理のない範囲でゆっくりと進めていくことが望ましいです。
よくある質問(Q&A)
Q1.障害者雇用の給料が低い理由はなぜですか?
障害者雇用の給料が低い理由は、業務内容と雇用形態にあります。
障害者雇用では、業務量を軽減するなど、体調や特性に配慮した業務が中心となり、一般雇用と比べて給与水準も低めに設定される傾向があります。また、契約社員やアルバイトなど非正規雇用が多いことにより、平均的に給与額が低いことが原因です。
Q2.昇給やボーナスはありますか?どんな企業が制度を整えていますか?
昇給やボーナスは、企業によって大きく異なります。
大手企業や上場企業、特例子会社では、障害の有無に関係なく評価制度を導入しており、昇給・賞与の実績がある会社も存在します。
一方、中小企業や非上場企業では、昇給制度がない場合もあります。
求人票や面接で「評価制度」「昇給実績」を確認することが重要です。
Q3.ADHDやうつ病など精神障害でも安定した収入は得られますか?
安定した収入を得ることは可能です。
ポイントは、体調に合った働き方と職場選びです。短時間勤務から始めて徐々に勤務時間を増やす、在宅勤務を活用するなど、無理のない働き方を選ぶことで、長期的な就労が実現しやすくなります。また、障害年金や支援制度を活用することで、安定した収入につながります。
Q4.障害者雇用から一般雇用になると給料は上がりますか?
多くの場合、給料は上がります。
障害者雇用は、業務内容や勤務時間が限定されることが多く、給与水準も低めです。一方、一般雇用に転換すると、昇給・賞与・手当が充実し、年収が100万円以上アップするケースもあります。ただし、体調や働き方のバランスを考えることが大切です。
Q5.障害者雇用でも年収500万円を目指せますか?
可能ですが、ハードルは高いといえるでしょう。
そもそも、日本の労働者の全国平均年収は約460万円(注7)です。
この水準を超えて年収500万円を目指すには、正社員として専門スキルを活かすポジションに就くことや、管理職になることが必要になるケースが多いです。
たとえば、ITエンジニア、経理、法務などの専門職や管理職であれば、障害者雇用でも高年収を実現している事例があります。また、スキルアップ、副業を組み合わせることも有効です。特に、プログラミングや簿記などの資格取得は、キャリアの幅を広げる大きな武器になります。
(注7)参照:令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省
まとめ|給料だけでなく「働き方の選択肢」を知ろう

「障害者雇用で本当に生活できるのかな?」
「この給料で将来やっていけるのかな?」
「自分に合った働き方なんて、本当に見つかるの?」
そんな不安を感じるのは、あなただけではありません。
実際、給料(賃金/工賃)だけで生活するのは簡単ではないケースもあります。
でも、ここで大切なのは「金額(報酬)」だけで判断しないことです。
障害年金や自治体の支援、副業や在宅ワークを組み合わせれば、生活を安定させる方法はいくつもあります。
そして、スキルアップやキャリアチェンジによって、収入を増やす道も開けます。
働き方は一つではありません。
・安心した環境で自分らしく働きたい
・短時間勤務から始めて、少しずつステップアップする
・在宅ワークで体調に合わせて働く
など、ご自身のペース/ご自身に合った働き方を検討してみましょう。
今のご自身の状況を整理して、なりたい姿をイメージして逆算することから始めることで、未来の選択肢は必ず広がります。
その第一歩として、見学体験会に参加して、実際の職場をみるのはいかがでしょうか?
スタートラインでは、
といった多様な働き方を実現し、安心して長く働けるサービスを展開しており、見学体験会/オンライン説明会(無料)を随時実施しています。
・世の中にどんな仕事があるのか知りたい
・まずは安心した環境で働いてみたい
・自分にあった働き方をみつけたい
そんな方にとって、お仕事内容やリアルな現場を体感できる貴重な機会です。
まずは見学体験会/オンライン説明会(無料)から、あなたの“働く未来”を一緒に描いてみませんか?